※この記事はアフェリエイト広告を利用しています
はじめに
PT、OT、STといったリハビリ職は、国家資格を取得した後にさまざまな職場で働くことができます。しかし、就職活動では「どのような職場を選べばよいのか」「就職するときに何を基準に考えればいいのか」と迷う人は少なくありません。
実際に就職してから「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースもあり、職場選びはキャリアを左右する大きな分岐点です。そこで今回は、リハビリ職の学生が就職先を選ぶときに知っておきたい5つのポイントを解説します。
本ブログでは、入職1年目にやっておくべきことについても解説していますので、学生だけでなく新入職の方はぜひ参考にしてみてください。
1.病期や領域を把握しておこう
リハビリ職が活躍できるフィールドは非常に広く、病期(急性期・回復期・生活期)や領域(整形外科、脳血管疾患、小児、精神、在宅など)によって仕事内容や求められるスキルは大きく変わります。
多くの方は実習で様々な病期や領域を経験すると思います。その中で興味がある分野や楽しかった領域に進むと良いかもしれません。以下に私の経験からそれぞれどんな特徴があるか解説します。
急性期
救急搬送直後や手術後の患者を対象とするため、医学的管理が厳密でスピード感が重視されます。ベッドサイドでの早期離床、合併症予防、退院に向けた方向性の判断などが中心です。リスク管理が非常に重要視され、医師や他部署と積極的にコミュニケーションを取る機会が多いです。
発症早期のためほとんど動けない患者さんを車椅子に移乗させたり立位を取ってもらう必要があるため、介助の技術は必要です。業務としては、入退院も多いためリハビリ業務とは別に書類業務が多いです。
様々な疾患の知識やリハビリに関する循環器や呼吸器等のリスク管理を勉強するならおすすめです。
回復期
入院中の患者さんそれぞれのゴールを設定し、退院後の生活を見据えたオーダーメードのリハビリを行います。患者さんに合わせて課題の難易度や運動の負荷量を調整しながらリハビリを行っていくため目標に到達できた時の達成感は一番大きいです。
特に回復期では脳卒中の方に対して長下肢装具を使用して立位訓練や歩行訓練はリハビリに特化している病院が多いので、急性期と同様に介助技術が必要です。
その一方で、リハビリを拒否する患者さんや予後不良の方、退院先が決まらない方も中にはいますので、そのような方たちとも長い時間を過ごす必要があります。
生活期(維持期・在宅・施設)
自宅や介護施設で生活する人が対象です。機能回復というよりも「現状維持」や「生活の質(QOL)の向上」が目的となります。生活環境の調整や福祉用具の選定、家族指導など幅広い支援が求められます。
急性期や回復期とは違い一人の患者さんに対してリハビリする時間も限られているため、その中で如何にしてQOLの向上を目指すかが腕の見せ所です。業務としては、比較的時間の流れはゆっくりであるため、余裕をもって行う事ができます。
しかし、急性期や回復期では入院期間や医療保険でリハビリができる期限が決まっていますが、生活期の場合は介護保険でリハビリを行うため医療保険よりも長くリハビリを行います。そのため、何年単位で一人の患者さんとリハビリを行う事もあります。
自分がどの病期や領域に興味を持っているかを学生のうちに考えておくことで、就職活動で迷わずに済みます。「いずれ在宅で働きたいから、まずは回復期で経験を積もう」など、キャリアの流れをイメージしておくと良いでしょう。
介護保険について解説している記事もあるのでぜひ参考にしてください。
2.人間関係を知っておこう
病院だけでなく、どの会社でも同じですが、人間関係が良好かどうかで仕事のやりやすさは大きく変わります。特にリハビリ職は多職種連携が基本となるため、リハビリ科だけでなく、医師、看護師、ソーシャルワーカー、介護職、管理栄養士など、幅広い職種と良好な関係を築けているかは重要です。
チーム医療の雰囲気
就職見学や実習で病院に行った際には、職員同士の会話の様子や患者への対応を観察してみましょう。
また、「リハビリ科と看護部が対等に話し合っているか」「カンファレンスで意見交換が活発か」などを聞いたり見ておくとよいです。病院だと、医師の意見がかなり強く出ることも多いため、医師との関係が良好かどうかは非常に大切なポイントです。
上司や先輩の人柄
新人教育の方法や、上下関係などは職場ごとに大きく違います。厳しさはあってもサポート体制がしっかりしている職場もあれば、ただ放置されるだけの職場もあります。
実習中は教育している場面に遭遇する機会も多いため、教育担当者がどのような言葉遣いをしているか、どんな雰囲気で教育しているかを観察するとその職場の文化が見えてきます。
離職率や定着率
人間関係が悪い職場は、離職率が高い傾向があります。可能であれば、見学時に「新卒で入職した方はどのくらい続けていますか?」と聞いてみると、定着率を知る手掛かりになります。
また、若手とベテランが多く中堅が少ない職場は教育体制や人間関係に課題を抱えている可能性があります。就職を考えている職場の年齢層や経験年数の割合などを確認しておきましょう。病院のHPやインスタなどでスタッフの年齢層や経験年数を公開していることもあるので、事前にチェックしておくと良いでしょう。
実体験から感じたこと
人間関係は仕事をするうえで非常に大切です。私自身、入職した頃は先輩によく飲みに連れて行ってもらいました。仕事の話はもちろん、プライベートの相談も気軽にできるようになり、自然と信頼関係が深まっていきました。飲みニケーションを通じて仕事の相談がしやすくなったことで、結果的に業務もスムーズに進められるようになったと感じています。もちろん最近は飲み会の文化が薄れつつありますが、職場内で信頼できる人間関係を築くことが、自分に合った働き方につながると強く実感しています。
3.教育や研修の制度を把握しよう
国家試験に合格したからといって、すぐに一人前になれるわけではありません。臨床現場では学び続ける姿勢が求められるため、教育・研修制度の有無は非常に重要です。
新人教育
- OJT(On the Job Training)として先輩がマンツーマンで指導する体制があるか
- 定期的なフィードバックや面談があるか
- 体系的な研修制度が整備されているか
こうした制度が整っていると、安心して臨床経験を積むことができます。その一方で、取得単位数などのノルマを最優先して教育に力を入れていない職場もあるため、そのバランスも確認しておくとよいでしょう。
院内研修・勉強会
定期的に症例検討会や講習会が開かれている職場では、最新の知見や臨床スキルを学びやすい環境があります。自分の専門性を伸ばしたい分野に関連する勉強会があるかどうかは大きなポイントです。
しかし、プライベートを優先した人にとっては、これらの勉強会が自身にとって重荷になる可能性もあります。自分のライフスタイルに合うかどうかも考える必要があります。
学会や外部研修への参加支援
学会発表や外部研修への参加を奨励しているか、交通費や参加費の補助があるかもチェックポイントです。職場によっては「学会発表をすることが当たり前」という職場もありますし、全く発表していない職場もあります。
HPに学会実績が掲載されていたり、病院内に学会のポスターが掲示されていたりする場合はその職場の教育・学習への姿勢がうかがえます。
実体験から感じたこと
私の入職した職場は多くのスタッフが学会発表をしており、臨床業務にも熱意を持って取り組んでいました。その姿を見ていると「自分も頑張らなければ」という気持ちになり、自然と学ぶ意欲が高まりました。こうした勉強熱心な環境に身を置くことで、自分自身も前向きに成長できたと感じています。学びに対して熱を持っている人は、あえてそのような環境を選ぶことが、自分を大きく伸ばすきっかけになると思います。
4.福利厚生や給料などを把握しよう
就職活動では「やりがい」や「学び」を重視する人が多いですが、実際に働き続けるためには生活の安定が欠かせません。給料や福利厚生を事前に確認することは現実的であり、とても大切な視点です。
給与水準
リハビリ職の初任給は大きな差が出にくいですが、昇給制度やボーナスの有無によって年収は変わります。「5年後、10年後にどのくらいの給与が見込めるのか」を確認しておくと安心です。
昇給率や賞与は勤務先によって異なり、賞与が年に何か月分支給されるかも重要なポイントです。実際に、同じ職場でも「他施設より賞与が多く、結果的にリハビリ職の平均より高い給与がもらえている」というケースもあります。生活の安定度はこうした違いによって大きく変わります。
勤務形態
- 残業の有無や残業代の支給状況
- シフト勤務か、土日祝休みか
- 休みの希望は通りやすさや有休消化率
これらはライフスタイルに直結する要素です。将来的に結婚や出産を考える場合、ワークライフバランスを保てるかどうかはとても重要です。たとえば、結婚式や新婚旅行で長期休暇を快く認めてくれる職場もあり、安心してライフイベントを迎えられる環境は働きやすさに直結します。
さらに、子育て中のスタッフに対して「土日休みを優先してシフトを調整してくれる」といった配慮を行っている職場もあります。このような柔軟性があるかどうかも、長く働く上で大きな差になります。
福利厚生
住宅手当、通勤手当、資格取得支援、退職金制度なども見ておきましょう。法人によっては保育園との連携がある場合もあり、ライフステージに応じた支援が手厚いところもあります。
「給与だけでなく、福利厚生や職場の雰囲気を含めたトータルの待遇」を把握することが、就職後の満足度につながります。実際に働く先輩から体験談を聞いたり、見学時に質問してみるのもおすすめです。
5.長期的なキャリアから判断しよう
就職はゴールではなく、キャリアのスタートです。長い人生を見据えたときに「自分はどのようなリハビリ職として成長したいのか」を考えることが大切です。
専門性を深めたい人
認定理学療法士や専門作業療法士などの資格取得を目指す場合、臨床経験の積み方や症例数が重要です。その分野の症例が豊富な職場かどうか、学会発表や研究活動に積極的かどうかを確認しましょう。
幅広い経験を積みたい人
複数の病期や領域を経験できる法人に勤めるのも一つの方法です。法人内で異動が可能であれば、キャリアの幅が広がります。
将来的に在宅や教育に進みたい人
在宅分野や教育・研究の道を考えている場合、病院や施設での経験が基盤となります。数年後のキャリアを逆算して「今の職場でどのような経験ができるか」を考えておくと、キャリアの方向性がより明確になります。
管理職や外部活動も視野に入れる
昇給や賞与といった給与面は、管理職になるかどうかによって大きく変わります。そのため、職場の規模感や管理職の人数を把握しておくことも重要です。一般的に「スタッフ数の約10%が管理職」と言われており、例えば30人規模の職場なら3人は管理職になれる計算です。管理職になりやすい環境かどうかは、将来の収入やキャリア形成に直結します。
さらに、外部活動を積極的に行っている上司や先輩がいれば、そのネットワークに参加させてもらえることもあります。学会活動や地域リハビリテーションへの関わりは、自分のキャリアを広げる貴重な機会になります。
まとめ
リハビリ職の学生が就職活動をする際に知っておきたいポイントは以下の5つです。
- 病期や領域を把握しておこう – 自分の興味やキャリアを考えて選択する
- 人間関係を知っておこう – 多職種連携や職場の雰囲気を見極める
- 教育や研修の制度を把握しよう – 成長をサポートしてくれる環境があるかを確認する
- 福利厚生や給料などを把握しよう – 安定して働ける待遇かどうかをチェックする
- 長期的なキャリアから判断しよう – 将来の自分をイメージして逆算する
就職は人生の大きな選択ですが、焦る必要はありません。しっかり情報収集し、自分の価値観や将来像に合った職場を選ぶことで、安心してリハビリ職としての第一歩を踏み出せます。
この記事の中で、ひとつでも就職活動の参考になればうれしいです。
これからも理学療法士についてや身体に関することを解説していきますので今後もご覧頂けると幸いです。
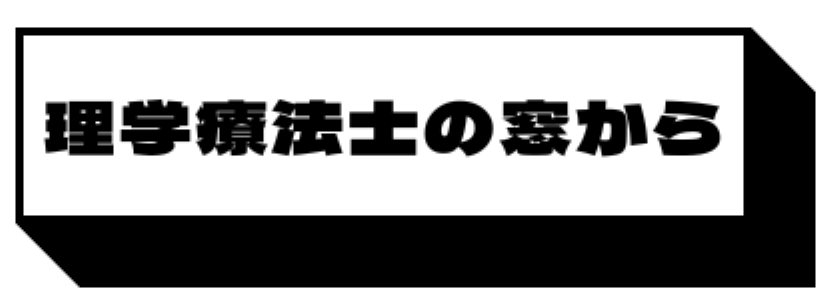





コメント