※この記事はアフェリエイト広告を利用しています
「リハビリ病院を退院するけれど、この後どんな支援が受けられるの?」
「介護保険の申請ってどうやるの?」
リハビリを経て自宅へ戻る際、患者さんやご家族が最も不安に思うのは「退院後の生活」です。介護保険制度を理解し、申請からサービス利用までの流れを押さえておくことで、退院後の生活がぐっと安心になります。この記事では、理学療法士の視点から 介護保険の申請方法 → 認定 → 利用できるサービスの種類 をわかりやすく解説します。
この記事を読むべき人
- リハビリ病院に入院している方
- ご家族がリハビリ病院に入院している方
- リハビリ病院に勤務しているコメディカルの方
1. 介護保険とは?

介護保険制度は、要介護状態になっても安心して生活できるように国が整えた仕組みです。
リハビリ病院を退院したあと、スムーズに在宅生活へ移行するための大切な制度になります。
- 対象者:65歳以上、または40歳以上で特定疾病がある人
- サービス内容:訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなど
- 費用負担:原則1割~3割負担(所得により変動)
特定疾病は16種類あり、対象となる場合は40歳からでも介護保険を利用できます。
詳しくは厚生労働省のHP(特定疾病について詳細)を参考にしてください。
2. 介護保険の申請方法
介護保険を使うには「要介護認定」の申請が必要です。
申請の流れ
- 市区町村の介護保険窓口へ申請
本人の他に家族、親族、地域包括支援センターの職員でも代行可。 - 訪問調査
認定調査員が自宅や入院先を訪れ、心身の状態を確認。 - 主治医意見書
主治医が病状・リハビリ状況を記載。 - 介護認定審査会
調査結果と医師意見書をもとに、要介護度が決定。
申請に必要なもの
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
申請書は、市役所や福祉事務所などでもらえます。 - 介護保険被保険者証
65歳以上の方にはご自宅へ郵送で送られます。紛失した場合は再発行してもらうことが可能です。 - (加入者のみ)健康保険の被保険者証
認定までの期間
申請から結果通知まで 約1ヶ月程度 かかります。リハビリ病院に入院している方の多くは、退院後に介護保険でのサービスを使用して自宅で生活を過ごすことになるため、申請は早めにしておく方がよいでしょう。
厚生労働省のHPでは、認定結果は原則30日以内と記載がありますが、自治体により結果通知が遅れることもあるため注意が必要です。
3. 要介護度とサービス利用の関係
介護保険で受けられるサービスや利用料の上限、入居できる施設は、認定された要介護度によって異なります。
- 要支援1・2
→ 自立支援や予防を目的としたサービス(例:介護予防通所リハビリ、訪問リハ) - 要介護1~5
→ 身体介助や生活支援が中心。要介護度が高いほど利用できるサービス量が増える。
介護保険の利用には、ケアマネジャーが作成するケアプランが必要です。
- 要支援者→地域包括支援センターのケアマネジャーが担当
- 要介護者→居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当
介護サービスの詳細は厚生労働省HP(介護サービス情報公表システム)を参考にしてください。
4. リハビリ病院退院前に確認しておきたいこと
リハビリ病院を退院する前には、実際の生活に直結するポイントを確認しておくと安心です。特に以下の点は見落としがちな部分です。
- 食事の形態
きざみ食やとろみ付きの水分が必要かどうかを主治医や言語聴覚士に確認しましょう。きざみ食やとろみの水分は普段の料理とは準備方法が異なるため、退院後すぐに対応できるようにしておくことが大切です。
- 排泄管理
入院中にオムツを使用しているか、普通のパンツでも失禁がないかは確認しておきましょう。失禁がある場合はパッドのみで対応できるのか、自身で交換が可能かは重要です。
- 入浴の方法
自宅で浴槽に入れるのか、シャワーのみ済ますのか、あるいはデイサービスでの入浴を利用するのかを検討します。浴室環境によっては手すりやシャワーチェアの導入も必要になります。
- 退院後の運動機会
退院後に運動の機会が必要かどうかをリハビリスタッフに確認しておきましょう。デイケアはマシンを使った訓練が中心のため、マンツーマンの訪問リハビリを選んだ方が良い場合もあります。
5. リハビリ病院から退院後によく利用されるサービス

退院直後は、まだ身体機能が安定せず、生活に不安が多い時期です。そのため、以下のようなサービスを組み合わせることが一般的です。
デイケア(通所リハビリ)
日中に施設へ通い、集団リハや機能訓練を受けられるサービス。
- 特徴:自宅への送迎あり、社会交流の場としても活用できる。
- メリット:孤独感の軽減、体力維持。
訪問リハビリテーション
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅に訪問し、生活場面に即したリハビリを行います。
- 特徴:自宅の段差や生活動線を実際に確認しながら練習できる。
- メリット:実際の自宅でリハビリを行える。マンツーマンでリハビリができる。
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、入浴・食事・排泄などの介助や、掃除・買い物などの生活援助を行う。
※日常生活の援助の範囲を超えるサービスは不可
福祉用具レンタル・住宅改修
杖、歩行器、手すりなどをレンタル・設置できる。
- 特徴:自宅の環境や生活に合わせて調整できる。
- メリット:レンタルのため故障や破損にすぐ対応してくれる。
6.理学療法士がおススメする介護保険サービス
退院後の生活をより安心して過ごすために、理学療法士の視点から以下のサービスをおすすめします。
- デイケア(通所リハビリ)
身体機能の維持・向上だけでなく、他の利用者との交流による社会参加の場としても有効です。孤独感の軽減や生活リズムの安定にもつながります。
- 訪問リハビリ
家事や買い物に不安がある場合、自宅環境に即した動作訓練ができる訪問リハビリがおすすめです。実際の生活動線に合わせた練習や環境調整を行うことで、より安全に自宅での生活を続けられます。
- 福祉用具の活用
歩行器などの福祉用具は介護保険でレンタルできるため、退院前に準備しておきましょう。病院内で練習しておくと退院後すぐに安心して使えます。また、服薬カレンダーを活用し、病院で使い方を確認しておくと、自宅での服薬管理もスムーズになります。
7. サービス利用のポイントと注意点
- 早めの申請:申請から認定まで約1か月かかるため、退院前に準備を。
- ケアマネジャーとの連携:希望する生活スタイルをしっかり伝えること。
- 医療とのつながり:退院後も主治医のフォローを受けつつ、サービスを利用する。
- 費用面の確認:1割~3割負担に加え、自己負担分が生活に影響しないかチェック。
まとめ
介護保険は、リハビリ病院を退院したあと、自宅生活を安心して続けるための大切な制度です。
- 申請は早めに行う
- 要介護度によって使えるサービスや限度額が変わる
- 訪問リハ・デイケア・福祉用具などを上手に活用する
これらを理解しておくことで、「退院後の不安」を「安心」に変えることができます。ご家族と一緒に情報を整理し、必要な支援を受けながら生活を続けていきましょう。
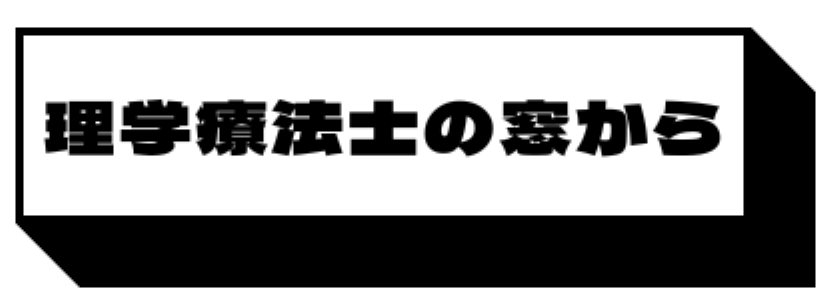
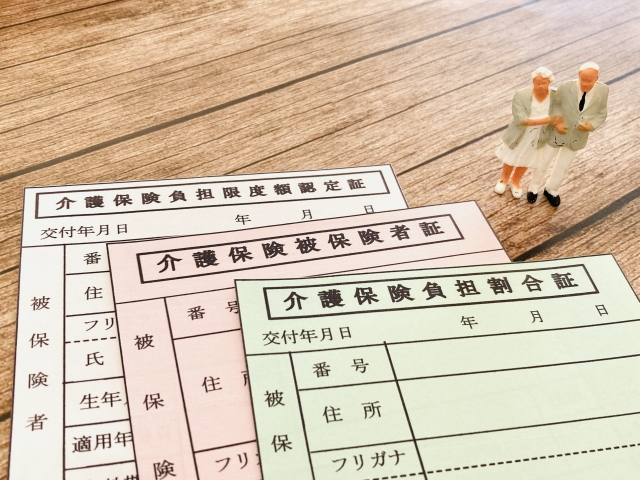


コメント